ワイングラスの種類 2
| 【ワイングラスの各部の名称・解説】 |
| ワイングラスは、だいたい左図の様な3つのパーツから構成され |
| ています。 |
| <カップ部> |
| お酒が入る部分です(当たり前!)。機能やデザインによって様々 |
| な形状があります。 |
| 機能面を重視する場合は、前頁に記載した様に、お酒によって適 |
| 量を考え、口の開き型や反りは、香りの広がりや傾けた時の液体 |
| の流れを十分考慮します。(オイラは考慮出来ないが。) |
| <ステム部> |
| いわゆる「足」の部分。ワイングラスを持つ所になります。 |
| 機能としては、カップ部を持つと手の熱がワインに伝わり、ワイン |
| が、必要以上に暖まりバランスが崩れてしまいます。 |
| よってこのステムを還し、持ち手とする事で手の熱によるワインの |
| 暖まるのを防ぎます。 |
}

カップ
}
ステム
}
フット
| 引き足 |  |
カップの、一部分のガラス生地を細く引き伸ばし、棒状に伸 ばしたもの。 18世紀のイギリスで流行した形で、現在では最も一般的な ステム。(当時のイギリスでは、グラスの重量に応じて税金 が掛けられていた為、より軽量なグラスを目指した結果の産 物と言われてる。) |
| 付け足 |  |
カップ部を作った後に種を付け、それを引伸ばしたステム。 |
| ブローステム |  |
吹き竿で吹いたガラスを付け、中を空洞にしたもの。 ステム部のガラスを吹く工程以外は、付け足と基本的に同じ。 (付け足の1つのバリエーション。) |
| 装飾ステム | こちらも付け足の1種。 ベネチアングラスに多く見られ、白鳥や、イルカ、龍などの 動物や植物といった、様々な形の物がある。 カップ部に種を付けてから、形を作っていくか、予めパーツ として別に作っておいた物を、後で溶着したりする。 |
| <フット部> |
| グラス全体を支える部分。原則的にカップ部の直径と同じ物が多いです。(その方が安定する。) |
| 作り方としては、「ブローフット」と「台広げ」と呼ばれる道具を使って行う、この2種類があります。 |
| ・ブローフット |
| 吹き竿にて吹いた玉を付けて、お皿状に広げて台を作る方法です。 |
| この方法ででは、台自体のガラスを薄く作れたり、色や模様を付けたり、変化にとんだ形状を作 |
| る事が出来ます。 |
| が、しかし・・・ そのぶん作業が大変です。(笑) |
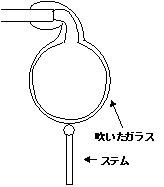 |
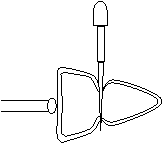 |
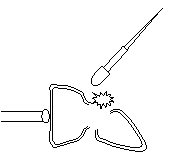 |
| 1.ステムの部分にブローした種を溶着する。 | 2.ブローした種をハサミで切っ て、適当な箇所で括りを入れる | 3.洋バシやピンサーの背中 で、先端部分を落とす。 |
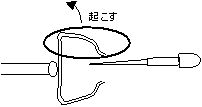 |
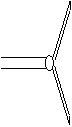 |
おしまい |
| 4.洋バシで丸印の部分を”えぃ!”と起こす。 | 5.そうすると多分出来上がる(笑) |
| ・台広げ(フットツール) | 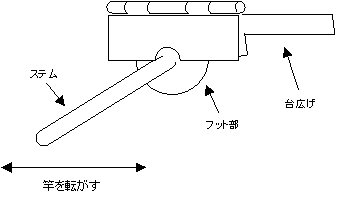 |
| フット部のもう1つの作り方は、この台広げと言う | |
| 道具を使って行う方法です。 | |
| 家にあるドアのヒンジ(パタパタするヤツね)を改良 | |
| したフォルムを持ち、ステム部に巻かれたガラスの | |
| 種を絵のように挟み込んで、竿を転がせば簡単に | |
| 出来ちゃいます。 | |
| だから、量産には適してると思いますよ。 | |
| ちなみにこの道具、私が吹きガラスやっていて、 | |
| 洋バシの次にビックラこいた道具です。 | |
| ホント、よく考えつくよね ・ ・ ・ ・ |